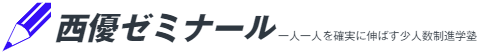【本紹介】学力の経済学 中室牧子
こんにちは!
西優ゼミナールの河合です。
今日の本紹介
久しぶりに本紹介をやります。
知ってる方も多いかと思います。
こちらです。
学力の経済学

商品はこちらから↓↓↓↓↓
中室牧子 ディスカヴァー・トゥエンティワン出版
この本は2015年に出版され、30万部のベストセラーになりました。
私も知ってはいましたが、ちゃんと読んだことがなかったので少し気になっていました。
マンガで読めるバージョンも出ているので、気軽に読みたい人はそちらでもどうぞ。
内容に関して
経済学というタイトルから経済学の難しい話をされるかと思いきやそんなことはありません。
はっきりいうと完全に「教育本」です。
ですので、今回は子どもの教育について参考になる箇所について紹介致します。
内容紹介前に重要事項の確認
本書ではたびたび因果関係なのか、相関関係なのかについての議論がなされます。
因果関係とは原因があって結果があるという関係性(一方通行の関係)で、相関関係とは2つの事象双方に関係性があるかです。
例を挙げますと、学力が高い子どもは家庭で読書をしているという調査結果が出たとします。
ですが、この因果関係と今回の内容だけに関わらず、身の回りの様々な事象について常に考えなければいけません。
上の例では読書以外のことを鑑みず、読書だけ頑張れば、学力が高くなると勘違いしてしまう人もいるでしょう。
(読書をすれば様々な知識を得たり、読解力が上がったりするかもしれませんが、それがすべてではありません。)
それでは気になる内容5つ紹介します。
- 子どもをご褒美で釣ってはいけないのか?
- 教育にいつ投資すべきか?
- 非認知能力の重要性
- 子どもは褒めて育てるべきなのか?
- ゲームは子どもに悪影響を及ぼすのか?
気になる5つの内容
①子どもをご褒美で釣ってはいけないのか?

「次のテストで450点以上だったらスマホ買って!」みたいなことは中学生の保護者であれば一度は耳にする言葉だと思います。
「まあそれぐらいしたら勉強も頑張ってくれるしいいか...」
と多くの保護者はなるのではないでしょうか?
結論から申し上げますと、ご褒美で釣るのは子どもにとってプラスの効果をもたらします。
ただし、何に対してご褒美をあげるかが重要になってきます。
本書ではインプットとアウトプットの2つで大規模実験を行いました。
インプットとは「本を一冊読む」「宿題を終わらす」「学校にちゃんと出席する」などです。
アウトプットとは「テストの点をあげる。」「通知表の成績を良くする。」などです。
結果はどうなったかというとインプットにご褒美を与えた子どもたちの方が学力テストの結果が良くなりました。
直感的にはアウトプットの方が結果につながるイメージですが、実際は逆の結果となりました。
この原因はしごく単純で、インプットは子どもが何をやるべきかが明確であるのに対し、アウトプットは何をすればいいか具体的な方法が示されておらず、子どもも何をしたらいいか漠然としているからです。
やむを得ずアウトプットに対してご褒美をあげるにしても、大人が具体的な手段を教えてあげる必要があります。
そうすれば、インプットに対するご褒美を同じ効果があるそうです。
②教育にいつ投資すべきか?

将来のためと思って、子どもに習い事をさせたり、塾に通わせたりしている親御さんの方がほとんどかと思われます。
ではいつから教育に投資すべきかというと早ければ早いほどリターン(子どものためになる)が大きくなる実験結果が出ています。
こちらの図は人的資本投資の収益率というグラフです。

学力の経済学より引用
収益率と年齢は反比例の関係になっています。
幼少期(早い段階)に投資することが子どものためになり、小中高、大学生となっていくにつれてためになる度合は減少していきます。
そしてここでは投資のことを人的資本投資と表現しています。
教育の投資というと学習塾へ通わせることを想像しがちですが、そうではありません。
これは次項の非認知能力も含めた投資です。
勉強以外に家族で旅行に行ったり、課外活動をさせたり、子どもに新しい経験をさせることでもあります。
なるべく子どもが小さい年齢のときから色々なことに触れさせて知的好奇心を駆り立てたり、興味の幅を広げることが重要になってきます。
③非認知能力の重要性
学力の重要性は言わずもがなですが、本書では学力(テストの点や通知表の成績)以外の重要性についても述べています。
具体的に非認知能力とは「忍耐力がある」「意欲的である」「社会性がある」などの人間の気質や性格的な特徴を指します。
これらの非認知能力は将来の年収、学歴や就業形態などの労働市場における成果に大きく影響することがわかっています。
実際に勉強だけがとびぬけてできても社会で活躍できないことは容易に想像できます。
そして重要な非認知能力を本書では2つ取り上げています。
①自制心
目先の誘惑に負けずに、自分がすべきことを我慢して遂行できる力です。
人間というのは目先の利益にどうしても目が行きがちです。
ここでの自制心とは我慢強さや忍耐力ともとれそうです。
②やり抜く力
これを本書では「非常に遠い先にあるゴールに向けて、興味を失わず、努力し続けることができる気質」と定義されています。
才能とやり抜く力の間には相関関係がなく、また才能があっても「やり抜く力」がないために成功に至らない人も少なからずいたようです。
④子どもは褒めて育てるべきなのか?
「褒めて伸ばす」という言葉がありますが、果たしてどうなのでしょうか?
結論から申し上げますと、むやみやたらに褒めるのではなく、子どもの努力について褒めてやることが一番効果的だそうです。
やればできるなどとどんなこと(子どもの能力のよさ)に対しても褒めてしまうと実力の伴わないナルシストになりかねません。
実際には「今日は○○時間勉強できたんだね」や「今月は一度も遅刻欠席がなかったね」と具体的に子どもが達成できたことに対して褒めることが重要です。
⑤ゲームは子どもに悪影響を及ぼすのか?

家ではゲームばかりして、、、と私自身、懇談でも何度か耳にしたことがあります。
結論から申しますと、ゲームは悪影響を及ぼしません。
ただし、1日1時間から2時間程度であればです。
(2時間以上となると知能の発達や学習時間に空く悪影響となるようです。)
また保護者として気になるのは暴力的な描写が含まれるゲームを子どもがすることで同じような行動をしてしまうという心配も問題ありません。
子どもたちもゲームの中のことを現実世界でやろうと思うほど愚かではありません。
個人的にも最近のゲームは良くできています。
オンラインを前提としていたり、相手がコンピュータではなく人であったり、複雑性が高いです。
ゲームをすることで創造性や忍耐力、思考力を鍛えられるのは大人から見ても明らかです。
ストレス発散にもなりますしね。
もちろんゲームのやりすぎには要注意ですが。
まとめ
今回は教育本について紹介させていただきました。
保護者の方としてどうやって対処すべきか、本当にこのやり方でいいのか、細かいところを教えてくれる本となっている気がします。
因果関係なのか相関関係なのか、ちゃんとエビデンスがあるのか、このあたりは日頃から気にかけておくべきです。
1つ注意なのは、本に書いてあることを鵜呑みにすることです。
本書で紹介したデータにも必ず外れ値が存在します。
相手をしているのは人間なので、必ずしも同じ結果になるとは限りません。
自分の子に合わないと思えば変える必要はあります。
教育だけでなくすべてのことに例外が必ず存在します。
そこをまわりの大人たちが見極めてあげましょう。
それでは!